水の排水館① ![]()
●一般的な排水(下水)の区別
1.敷地内の排水
①建物内排水
②屋外排水 敷地内・一般敷地外
2.公共下水道
◆敷地内排水の種類とその器具 排水の種類 汚水・雑排水・雨水
排水の方式
排水方式 建 物 内 公共下水道 合流式
・汚水+雑排水 ・雨 水 ・汚水+雑排水+雨水 分流式
・ 汚 水 ・ 雑排水 ・ 雨 水
・汚水+雑排水 ・ 雨 水 排水管 排水横管は使用箇所によって,管径および勾配を考える。
管径75mm以下は1/50,100mmは1/100,150mm以上は1/200を最小とする。
屋内汚水配管は,1/50〜1/100程度とする。トラップ 排水管内の悪臭,有毒ガス,害虫などが排水管を伝わって室内に逆流するのを防ぐ目的で設けるもので,排水設備では欠くことのできないものである。 トラップの種類と特徴
トラップの種類 特 徴 Sトラップ ・一般によく用いられる.
・サイフォン作用をおこしやすい.
・自浄作用が強い.Pトラップ ・最も多く用いられる.
・Sトラップよりサイホン作用を起こしにくい.
・自浄作用が強い.Uトラップ ・排水横管の屋外本管に接続する末端に設ける. ベルトラップ
(わんトラップ)・床排水に使用される.
・ベル型金物が取り外されるとその機能を失う.ドラムトラップ ・厨房流しなどに使用される.
・自己サイホン作用は起こさない.封水深は5cm〜10cm程度とする。 トラップを二重に設けると,2つのトラップの間に空気だまりを生じ,流水を阻害することとなる。 封水破壊の原因 封水が蒸発して,失われる。 トラップに糸類などが引掛かったような場合に,毛管現象により封水が失われる。 排水が器具から満水状態で流れ出すと,器具,トラップ,排水管と切れ目なくサイホン管を形成して封水が流れ出てしまう現象。 そのトラップと共通の排水立管をもつ上部器具の排水が,満水状態で落下した後に低圧空気によって封水が失われる。 そのトラップと共通の排水立管をもつ上部器具の排水が,満水状態で落下する際に生じる高圧空気によって封水が,器外に跳ね出す。 阻集器 排水中に混在する砂,油,髪の毛など特定のものを除去して,排水管の閉塞を防ぐ器具である。
グリーストラップ・ヘアートラップなど通気管 通気管は,トラップの封水が破られるのを防止することを目的とするあ る。
また排水を円滑に流すために排水管内と外気を連結させて, 排水管の圧力 変動を緩和するために設ける。
なお,通気管の末端は,最上階器具のあふれ縁より15cm以上立ち上げ,窓等 の換気用開口部から十分離して,大気中に開放する。間接排水 汚染や衛生上の問題が生じやすい機器からの排水は,一度大気中で縁を切り,間接排水としなければならない。
給茶器,食器洗浄機,洗濯機,給水タンク,業務用厨房流しなど。
なお,家庭用の台所流しは,ベルトラップやドラムトラップを設置することにより,関接排水とせず,直接排水としてよい。排水タンク 有効内径60cm以上のマンホールを設ける。 汚水排水ます 汚物が滞留しないように,底にインバートを設ける。 雨水排水ます 下水管に土砂などが流れ込まないように,底に泥だめを設ける。
衛生器具とは、英語の"sanitary wear"の和訳であり、空気調和、衛生工学会規格HASS 206-1991では、次のように定義している。
「水を供給するために、液体もしくは洗浄されるべき、汚物を受け入れるために、または、それを排出するために設けられた給水器具・水受け容器・排水器具および付属品をいう。」 衛生器具は、これが複数組み合わされて使用される場合に、衛生器具設備と称し衛生的な生活環境を創造、維持するために必要な設備である。
衛生器具とは
衛生器具とは、建物内とその敷地内(輸送機関内)において、湯、水を供給するため、もしくは洗浄されるべき汚物を受け入れるため、あるいはそれらを排出するために設けられた水受け器、及びそれに伴う装置を総称した名称である。
水受け器および装置に付属装備されている給排水せん、給排水管、接続金物および取付金具を衛生金具と称し、その他これらに付随して使用される小器具を付属器具と称して、これらも衛生器具に含まれるものである。
すなわち便所、洗面所、浴室などに使用されている大小便器、手洗い器、洗面器、浴槽およびそれに使用されている水せん、排水金物などの給排水用衛生金具およびペーパーホルダー、化粧だな、鏡、石鹸入れなどの付属器具も含めて衛生器具と称するのである。
上記のように衛生器具をよく見てその構成を分類すると、給水ならびに給湯するための給水用器具(水せん類)、湯、水あるいは汚物、汚水を受ける器具(陶器および流し類)、器具と排水管を接続するための排水用器具(排水金物およびトラップ類)、およびこれらの器具を使用するために必要とされる付属器具(鏡、化粧だな、ペーパーホルダー、大便器用シート、石鹸入れ)に分類される。
衛生器具の四つの分類に関して、おのおのに必要にして十分な条件がある。現在使用されている衛生器具が必ずしも十分完全に条件を満足しているとは思われない。この条件はおのおのに特徴的な条件はもちろんあるが、まず一般共通的な条件を記述する。
(1). 吸湿性、腐食性のない、耐久性のある、容易に破損しない材料であること。
(2). 多くは建築仕上げ材料として室内に取付けられるので仕上がり外観が美的であると同時に衛生的であること。
(3). 器具の製作製造が容易であり、また取付が手軽に安全に接続できること。
(4). 汚染防止の点を特に配慮した器具であること
(1)に関しては材質に金属類が考えられ、その他合成樹脂製、ガラス製、陶器製などがあると思われるが、現状としては青銅製、黄銅製、真鍮製の金属製が多く使用されている。
(2)に関しては、まず機能を満足した上で形その他のデザインの問題があり、同時に色調なども考えられるが、器具全体のバランス、調和などに配慮をする必要がある。現在は金属製にクロム、ニッケルのめっきを施したものが使用されている。
(3)に関しては、器具の構造をできるだけ簡単に製作、製造部品の数を少なくして、かつ漏水を完全に防止できるものがよい。同時に管接続器具接続をできるだけワンタッチで接続できるような状態が理想的である。また、製品の重量も大きさも機能が満足できれば、軽く、小型のものが望ましい。
(4)の給水の汚染防止に関しては、給排水配管の水漏れ防止と同様に基本的な問題で、吐水口空間(間隔)、逆流防止、トラップの効用などを考慮して、衛生器具を組合せ、取り付けなければならない。
給水用器具に関して一般共通事項のうち特に注意をする事は、衛生器具として実際に組立て使用する時に給水吐水間隔を十分とり、なお十分な吐水口空間を確保できない場合は逆流防止器を使用することである。
湯水あるいは汚水、汚物を受ける器具としては、水洗いが完全にでき、排水後汚物などが器具の中に一切残らない状態の器具であるべきで、また排水管との接続に漏水がなく、完全に、簡単に、接続できなくてはならない。器具類にオーバーフロー口のあるものは、必ずその器具付属のトラップの上流にオーバーフロー水の排水を接続するようにする。
湯水あるいは汚水・汚物を受ける器具として普通使用されているものとしては、陶器製品、ステンレス製品、ほうろう引き製品、プラスチック製品、コンクリート製品などがある。
排水用器具に関しては、一般共通事項のほかに湯水あるいは汚水・汚物を受ける器具の排水口にできるだけ近接して必ずトラップを取り付ける。そして、その末尾を排水管に接続する、トラップとは排水管の一部に水封部を設け、下水もしくは汚水・汚物の流通に支障なく下水中のガスの室内への侵入を阻止できるように、設計・構成された排水器具である。
トラップの封水の深さは、排水管内の逆圧、サイホン作用などにより破られない深さが必要であり、普通使用されているものは50mm以上100mm以下、あまり深くすると自浄作用が弱くなり、排水詰まりを生じやすくなるので必ず掃除口を必要とする。
次に、これら器具の耐圧は一般に給水用器具は耐圧17.5kg/cmで最高使用圧力7.5kg/cmと定められている。排水用器具は、3.5kg/cm以上の耐圧を必要としているものが多い。
また、これら四つの分類の衛生器具に対する種類・形状・寸法・材質・機構・耐圧などに関する規格として日本工業規格のあるものが多く、主なものを別表に示す。
|
|
衛生器具は、その名の示すとおり、それを使う人にとって衛生的であることは言うまでもないが、快適性・安全性・利便性を兼ね備えていることが肝要である。 一般に、衛生器具は「衛生上の性能」と「環境的性能」を併せ持つ必要があるといわれている。
A 衛生上の性能・・・人体または人の住む内部環境の清浄度を維持するため、 必要十分な水を供給でき、かつ、使用した水や、汚水 を速やかに排出できること。
B 環境的性能・・・・衛生設備の配置と外観、その空間の形状と色彩、明る さや音の問題をとらえ、使用者に対し快適性・安全性 ・利便性を保持でき、維持管理も容易であること。
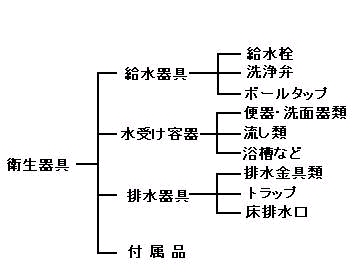
衛生器具の詳しい説明
衛生器具の材質として要求される条件
| 衛生陶器 | 特徴 |
| 衛生陶器は、他の材質のなかで最も衛生的条件にかなったものとされている。JIS規格では、大小便器をはじめ洗浄用タンク、洗面器、手洗い器、流し類を規定している。 | 耐酸性・耐アルカリ性で表面が硬質、こすり傷、引っ掻き傷が付かない。 平滑で汚れがすぐ分かり、掃除が容易である。 吸水性が少なく、変色せず、臭いが着かない。 弾力性がなく破損しやすいため、特に取り扱いと運搬に注意を要する。 金属との固定は、陶器との間に有効な弾性材を介する必要がある。 また、コンクリートなどに埋め込む場合は、陶器との外面は適切なる 被覆材で養生につとめる。 焼き物の関係上、寸法は不揃いがちとなり、取り付けに不都合が生 じることがある。 |
| ホーロー鉄器 | 特徴 |
| ホーロー鉄器は、鉄にホーローのうわぐすりを掛け、熟成したもので、 鉄材には鋼板製と鋳鉄製の2種類がある。 製品として、丸鉢洗面器、流し、浴槽などがある。 | 陶器に比べ「脆さ」がなく丈夫である。 ステンレス鋼より重く、陶器より軽い。 加工性に劣る。 衝撃に弱く、剥離する。 |
| ステンレス鋼製品 | 特徴 |
| ステンレス鋼板は主として、流しや浴槽に多く用いられ、その材質は 冷間圧延ステンレス鋼板 JIS G 4305 の SUS 430 と SUS 304 の2種類 である。 | 陶器に比べ「脆さ」がなく丈夫である。 ホーロー鉄器より軽く、運搬・取り扱いが便利である 加工性は容易といえないが、技術により解決できる。 他の材質に比べ、強度にすぐれている。 |
| プラスチック製品 | 特徴 |
| プラスチックの材質の種類はきはめて多いが、衛生器具を対象とするもの として、FRP,ABS,塩化ビニール、ポリプロピレン、ポリエチレン樹 脂などがある。耐水・耐薬品性にすぐれ、なおある程度耐熱性が要求される 場合もある。また経年に対し疲労劣化の少ないことが条件とされている。 FRPはこれらの条件に対しプラスチックの中で最もすぐれ、現在は浴槽に 広く使われている。 | 軽量で、運搬・取り扱いが容易である。 保温性があり、感触が柔らかい。 強アルカリ性を除く化学性に強く、耐久性がある。 カラーデザインが自由である。有機物なので材質の疲れ、色あせがある。 傷がつきやすい。 熱に対して弱い。 強アルカリ性に弱い。 |
水は人間の生活に不可欠であり、大昔は地下水や川などから取水し、使った水や汚物は大地に廃棄していたが、都市ができて人々が集中してくると水道や下水道を作らざるをえなくなってくる。したがって、現在のものほど完全なものではないが、上水道、下水道は紀元前数千年前よりあったことがエジプト、パキスタン、インド、メソポタミア、ギリシャ、ローマなどの古代遺跡に井戸、地下水路、下水路、便所などが発見されたことによって明らかになっている。
我が国においては、農業が開けてからはし尿は汲取り便槽を設け貯留後汲取って農家の肥料とした。我が国の本格的な水道は江戸時代に大きな城下町に簡易なものが設けられたのが最初で、東京の神田上水や玉川上水など6本の上水から成る江戸水道はこの代表的なものである。
給排水衛生設備について記せば、19世紀末頃より大都市に大規模建物が建設されるようになり、これに伴い給排水衛生設備の技術も確立されるようになった。米国は給排水設備技術の最も進歩している国であるが、同国に最初の給排水設備に関する規制は1881年5月30日にイリノイ州で施工されているが、同国では1933年の世紀博で給水系統における逆流に起因する死者98名を含む、1409名の赤痢患者発生という洗礼を受け、もっとも衛生に意を払っている給排水衛生設備を確立している。
給排水・衛生設備のことを英語でplumbingというが、これは昔鉛管を使用していたため、ラテン語のplumbium(鉛)に由来している。
排水器具について
湯水を受ける器具(衛生陶器など)の排水口と配水管を接続する器具の事を総称して排水器具という。すなわち衛生陶器に取出し金物または排水口金物を取り付け、その下部にトラップを使用し、配水管に接続する。排水器具はおもに銅合金金物を使用し、室内に露出される部分は、クロムめっきをした金物が使用され、室内に露出されない部分には鋳鉄製などが使用されている。
トラップと排水口金物
排水口金物は湯水を受ける器具陶器などにより排水を取出す金物で、陶器との接触部にはゴムパッキンをはさんでロックナット金物で締付けて漏水を防止している。また、管との接続は鉛管、鋼管、トラップ金物をはんだ付け媒介金物、ソケット、ふくろナットなどの金物で接続する。
配水管内を流れる水は、一般に重力作用を利用し自然流下をするので、給水管と異なり管内は満水で、水が流れる事はほとんどない。特に器具から排水をしないときは管内は空である。したがって、下水管の有害悪臭のガスは管内をそって室内に流入する。これを防止する為にトラップを設置するのである。
トラップの材質として鉛製、銅合金製、鋳鉄製、陶器製、ステンレス製などが使用され、必ず掃除口を考慮して作られている。水封の深さは5〜10cmである。これをあまり深くすると流水の抵抗を増し、通水力を減じ配水管詰まりを起こす原因となる。また、トラップは衛生陶器にできるだけ近接して取り付けることが肝要である。また、この排水配管が長いとトラップに入る水速が減じ、自洗作用が起こらず排水詰まりの原因となる。
配水管は勾配により汚水が流れ去り、管内は常に空の状態となる。したがって、管内の空気は器具配水口から室内に上昇してくるので、これを阻止するために設けるのがトラップである。トラップは、器具排水が速やかに流れ去ると同時に管内汚染空気が上昇しないよう常に封水深が保たれていることが最も大切である。
●トラップの必要条件
| Pトラップ | 説明 | ドラムトラップ | 説明 | Uトラップ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
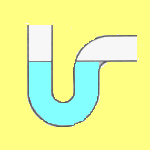 |
最も理想的な形で、一般に広く使用されている。 | 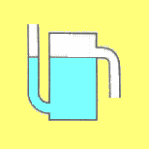 |
常に掃除をする必要があるため住宅向きではない。しかし、P型、S 型、U型トラップに比べ、封水部に多量の水が溜められるため封水が破られにくい特徴がある。 | 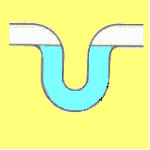 |
横走配管の途中に設ける場合か雨水用トラップとして使用される程度である。流速を阻害する弱点がある。 |
| Sトラップ | 説明 | わんトラップ | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
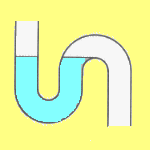 |
Pトラップに比べ自己サイホン作用を起こしやすく、封水を破るきらいがある。このサイホン作用を防ぐために通気管に配慮しなければならないが、器具排水管の径をトラップの口径よりひと口径大きくするなどといったことが一つの工夫であろう。一般住宅の台所流しでは、Sトラップ式が多く使用されている。 | 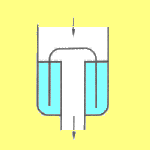 |
別名「ベルトラップ」ともいわれ、日本では一般に便所、洗面所、浴室、などの床排水、または台所流しに多く使用されている。現在市販されている多くは、排水能力が弱くく詰まりやすいために使用者は目ざらを外し、わんを取り外して排水することが多い。更に使用後にわんを元通りにすることを忘れがちである。このため、排水管内の臭気や下水ガスが室内に侵入し、居住者に対し非衛生な環境となっている。 | ||
| 自己サイホン作用 | 説明 | 毛細管現象 | 説明 | 蒸発 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
 |
洗面器などの器具で器具に満水された水がいっきに排水される時トラップ内の水は自己サイホン作用によって残らず配水管に吸引されやすい。この現象はSトラップの場合特に多い。 |  |
トラップのあふれ部に頭髪、糸くずなどがひっかかって垂れ下がった状態になる時、毛細管作用で徐々に封水が破られる。 | 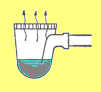 |
器具が永い期間使用されないで放置されていると、トラップ封水は自然に蒸発し空になる |
| 吸引作用 | 説明 | はねだし作用 | 説明 |
|---|---|---|---|
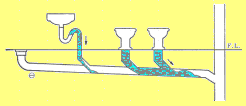 |
トラップに接続されている近くの配水管が満水状態に流れ、管内に真空状態が発生した時トラップ内の水は排水管内に吸引される。 | 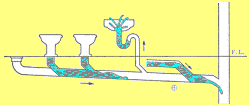 |
トラップに接続されている下流の配水管は、満水状態に流れている時上流の配水管から多量の排水があった場合中間の排水管内は正圧となり、その部分に接続される器具トラップ内の水は器外にはねだされる。 |