主な表面処理の概要と種類
 |
表面処理とその目的
金属はいずれも、大気中では永くはその特有色感と光沢を保つことが出来ません。空気中の酸素と反応して、酸化物を表面に作って曇り変色して錆びていきます。
また、金属は一般的に、素地のままでは柔らかくて傷付き易いとか、あるいは熱に弱いなど、そのままでは実用に供しにくい弱点を持っています。
そこで、使用する目的にしたがって、金属の表面を内部とは異なった性質にすることを「表面処理」といいます。
|
| 防食 |
亜鉛、すず、ニッケル、クロム等のメッキ。酸化皮膜処理(黒染め、アルマイト)。 |
| 美観 |
金、銀、銅、ニッケル、クロム等のメッキ。
塗装。電解・有機着色(ステンレスの着色やアルミニウムの着色等) |
| 硬化 |
クロムメッキ、アルマイト等。焼入れ。 |
| 耐熱 |
セラミック溶射等。 |
| 熱絶縁 |
セラミックコーティング等。 |
| 光反射 |
アルミニウムの電解研磨。銀メッキ等。 |
| 各表面皮膜の着き方の特徴 |
| メッキ、塗装、アルマイトによって、それぞれ皮膜の着き方が次のように異なっています。 |
| 1. |
メッキは角に良くつく |
| 2. |
塗装は、角の着きが悪い |
| 3. |
アルマイトは、素材の内側に付く |
メッキの種類と特徴
1.電気めっき
電解溶液中で品物を陰極として通電し、表面にメッキ金属を接析出させるもので装飾、防錆、機能とさまざまな目的に応じて比較的安価に適切な金属皮膜を付与できるため、自転車や音響、航空機、通信機、コンピューターから装身具、雑貨に至るまで広い用途に供されている。
①
銅めっき
銅は、塩素を含んだ水に簡単に侵され、亜鉛化銅として腐食する。従って、装飾めっき分野では銅単独で用いる事は殆どない。ニッケルあるいはニッケルクロームめっきの下地めっきとして利用される。一方、工業用の銅めっきは、その電極性及び均一電着性の特性を生かし広く利用されている。
②ニッケルめっき
ニッケルは、きわめて有用な金属である。空気や湿気に対して鉄よりはるかに安定である事から装飾、防食の両面に利用されている。但し、めっきの表面は空気中でわずかに変色するため、美観の付与と保持に役立つクロムめっきをして仕上げる場合が多い。ニッケルの厚めっきは、肉盛や電鋳意外にも適度の硬さや耐食性がかわれ多くの工業的用途がある。
③黒色ニッケルめっき
主として装飾用である。銅や黄銅めっきの上に黒色ニッケルめっきを行う。また、部分的にパフ研磨して銅の色調や黄銅の色調に黒を加味した、いわゆる古美仕上げは、家具金物や照明器具等に広く利用されている。
④クロムめっき
クロムは、磨くと高度の光沢が得られ、また硬さが大であり耐磨耗性、耐食性、耐熱性、密着性が良く、広く工業用に使用されている。めっきの最上層に施される薄いクロムめっきは、装飾用のクロムめっきであり、特有の深みを有する色調が、あらゆる部品の最終仕上げとして利用されている。
⑤黒色クロムめっき
漆黒調の皮膜が得られる代表的なめっきである。色調やつやは、めっき浴組成や電着条件によっても異なる為、各工場で微妙に異なる場合が少なくない。耐磨耗性に乏しい為、磨耗を伴う部品には不向きであるが、耐食性は大で塗装などほかの黒色化に比べて、最も耐久性のある皮膜が得られる。装飾以外の目的で利用される場合は、その光的、熱的特性が生かされる。代表的なものは、ソーラーシステムの太陽光選択吸収パネル、他に放熱板や、精度の必要な機械部品等に利用されている。
⑥工業用(硬質)めっき
多くの機械的特性をもつ代表的な工業用めっきである。使用目的が装飾以外のもので比較的厚い(JISでは5μm以上規定)めっきをいう。素地に直接、密着性の良い分厚いめっきを施す、というのが要求される基本的条件である。そのため、めっき前後の工数を煩わすものと成る。
⑦亜鉛めっき
亜鉛めっきは、主に鉄素地の錆止めに広く用いられる。めっき後のクロメート処理によって亜鉛表面の耐食性が増し、外観の美しさが備わる。
⑧カドニウムめっき
カドニウムは、電極電位が鉄に一番近い。耐薬品性が大きい、はんだ付け性が良い等の特性から多くのめっき用途を持った金属であるが、毒性が強く排水に入るカドニウムに厳しい規制が設けられたため、他のめっきに代えざるを得なくなった。現在では限られた用途のみ使用され、事業所も限定されてしまっている。現行部品についてはその代替の検討が続けられ、アルミのイオンプレーティングや、亜鉛ニッケル合金めっき等の報告がある。
⑨錫めっき
近年になって酸性浴の有機光沢剤が開発され、光沢性、はんだ付け性、防食性の優れた光沢めっきが得られるようになってからは、電子部品のめっきに注目されている。
⑩
金めっき
金は、耐腐食性、耐酸化性、電気、熱の良導体、低接触抵抗を兼ね備えている唯一の金属である。金めっきは、産出量の少ない金を最大限有効活用する方法として評価されている。装飾めっきでは多くの場合、金の色調を付与する事が主目的であり、外観に関しては一般に限度見本で行われることが多い。工業用としての金メッキは電子半導体部品を中心に極めて重要な機能的役割を果たしている。
⑪銀めっき
銀の電気電導性は金属中で最良という物性から、工業用めっきでは電気接点に利用されている。また、反射特性や耐食、耐磨耗にも優れている為、きわめて広範囲の分野で利用されている。また古来より尊ばれている銀の色調は、装飾品全般に利用され、特に装身具、食器等にりようされている。
⑫合金めっき
黄銅めっき・・・銅と亜鉛の合金皮膜で、合金比率によって金色は赤味から白味に変化する。
ブロンズめっき・・・銅と錫の合金皮膜で、耐食性が良好で平滑性に富む。錫が基本となると冴えた銀白色でハンダ付け性も良好である。
代用クロム・・・錫とコバルトの合金皮膜で、クロム色、つきまわりに優れている為、バレルめっきでの量産が可能である。
2.無電解めっき
溶液中での還元反応を利用して、品物の表面にめっき金属を析出させるもので、ごく一部の素材を除き、金属から非金属に至るまで広くめっき可能であり、膜厚精度もきわめて高い為、主に機能を重視した工場的用途に供されている。またプラスチックめっきの下地用として不可欠である。
①
無電解ニッケルめっき
近年市場が急速に拡大されてきた。複雑な形状に対しても膜厚のムラなく均一にめっきできる。加えて多くの機能的特性、電気的特性、物理的特性がッ評価されて、様々な分野で利用されている。ニッケルとリン(5〜13%)の合金めっきである。
②プラスチックめっき
汎用性から機能性に至るまで、様々な特性をもったプラスチックスが工業化され、広範囲な用途に供されている。成形技術の急速な進歩により、かなり複雑な形状の品物でも量産化が可能のため、軽量化、低コストと相まって、その用途は限りなく広がっている。プラスチックスは、塗装やメタリック仕上げホットスタンピング等各種の表面処理や成形技術によって、多彩な外観が付与されているが、プラスチックスを金属化(無電解めっき→電解めっき)して、商品価値を飛躍的に向上させうる最適な方法はプラスチックめっきといえる。
3・化成処理と着色
金属をある種の溶液中に浸漬し、表面に金属塩皮膜を生じせしめることを化成処理という。化成処理によって着色皮膜を得ることを化成着色(または化学着色)といい、電解による着色(または発色)と区別している。
①
クロメート処理
代表的な化成処理法であり、亜鉛めっきにおいては4種類の処理が行われている。それぞれ有色(虹色)、光沢(白色)、緑色、黒色の色を得ている。その他に銀めっき後のクロメート(変色防止用)、アルミニウム上のクロメート(別称アロジン)等がある。また電解によるクロメート処理もあり、近年、ニッケルめっき上の電解クロメートが薄金色皮膜を有する為、装飾用に注目されている。
②新しい化成処理
めっき皮膜を着色する方法で代表的なものは、亜鉛めっき製品を特殊な染料溶液に浸漬して、種々な色調(12色)を得るというものだが、より金属質感を生かした方法として、ニッケルめっきや銀めっきの上に特殊な硫化物浴で化成処理膜を作成する技術も実用化されている。色調も独特で、浸漬時間の経過とともに金色、赤色、青色に色が変化する。必要に応じ、仕上げにクリアーラッカー等のコーティングを施し、耐久性を向上させる。
③古美処理
古くから金属器の製作に不可欠の手法として活用されてきたものが、銅・銅合金の化成着色である。素材表面に硫化物や酸化物の皮膜を形成させる手法で、古銅色や青戻し、鉄錆色、斑朱銅、青銅色等の渋い色調が付与される。
④パーカーライジング(燐酸塩皮膜)
鉄などの金属材料を燐酸塩という水溶液に浸漬し、不溶性の燐酸塩皮膜を生成させる。通常、塗装の前後処理として行われる。これは表面が化学反応によりナシ地になるため、塗料ののりが良くなるためである。
⑤黒染め(四三酸化鉄皮膜)
濃厚カセイソーダに反応促進剤及び染料を加えた水溶液を140°前後に加熱沸騰させ、前処理(脱脂、脱錆)を加えた鉄鋼製品を浸漬、煮込むことによって四三酸化鉄皮膜を生じさせる。洗浄後、防錆油を塗布するが防錆力はめっきより落ちる。
4・キンリス
錆落しと同時に光沢を出す酸処理法をいう。光沢浸漬法、または化学研磨法ともいう。一般に黄銅製品に行われる事が多い。
5・溶融めっき
亜鉛や錫、アルミなどの金属を溶融した中に品物を入れ、それぞれ金属を付着させるもので代表的な例が亜鉛やアルミをめっきした鋼板で比較的大型の構造物やシートの厚膜がめっきされる例も多い。電子部品関係では、溶融ハンダもよく利用されている。
6.塗装
方法によって、吹き付け塗装、静電塗装、電着塗装、粉体塗装などがあり、いずれも広範囲に利用されている。多彩なカラー化がもっとも容易な技術である。防錆処理としてのダグロメタルも一種の焼付塗装。ポイントは焼付や紫外線などの硬化法にある。
ダグロタイズト・・・主成分の亜鉛と、介在の役目を果たす酸を含んだダグロタイズド処理液に浸漬塗装した後に、加熱し素地に焼き付ける。電気亜鉛めっきと比較すると耐食性、耐熱性、防錆性が優れている。また工程中塩酸処理を行わないので、水素脆性の恐れはない。素地は鉄、非鉄金属、軽金属及びそれらの合金類等、広範囲のものが処理可能である。
7.コーティング
有機高分子材料やガラス等の無機質材料で金属等を被覆させるもので、流動浸漬、スプレー溶射、静電、吹き付けなどがあり、いずれも数十〜数百μmのプラスチック粉末を、①
金属に付着後、溶融、②加熱金属に接触、溶融、③半溶融状態でコーティングという方法の単独または、組合せで施工せれる事が多い。
(参考)
メッキの呼称について
ねじ及び他の業界において、通常使用されているメッキの名称は、必ずしも規定のものではなく略称や俗称で呼ばれているものがある。それがまた一般化している現状をふまえ、それらについて注釈を書き加える。
①
ユニクロメッキ=電気亜鉛めっき光沢クロメート処理(1種)
クロメート処理における光沢仕上げは、米国、ユナイテッドクロミウム社が開発した処理方法で、その液はユニクロムデッィップコンパウンドといわれるところからユニクロメッキと呼ぶようになった。
②クロメートめっき=電気亜鉛めっき有色クロメート処理(2種)
本来クロメート処理と呼ばれるものは4種類あるが、有色仕上げ(虹色)のみに、この名称を使ってしまっている。しかも処理名称であるにもかかわらず、めっき名称として使用しているので、まぎらわしい呼び名である。
③カニゼンメッキ=無電解ニッケルめっき
カニゼン法という工法名であり、ゼネラルアメリカントランスポーティション㈱の商品名でもある。
④天プラメッキ=溶融めっき
金属を溶融した液は高温(融点)であり、そこに浸漬して出来上がった品物のメッキは厚膜であることから、天ぷら料理とよく似ているため俗称となった。
⑤ドブめっき=溶融めっき
めっき槽内の溶融液をドブにたとえて、呼ばれるようになった。
⑥ガラクロめっき=回転めっきでおこなった代用クロム3号めっき。または、クロム3号めっき
ガラとは回転めっきのことであるが、これはバレル(たる形の箱)に被めっき物を入れ、電解溶液中で回転させ、めっきする方法である。(バレルめっきともいう)その加工中に起こる音が、ガラガラと聞こえるため、それが俗称となった。クロはクロムのこと。また3号めっきとは研磨加工を行わないで、めっき加工をしたものである。
| 素地研磨の種類①
|
| 例えば同じ金属や同じメッキでも、素地研磨などの前処理の方法の違いによって、鏡面仕上げ・光沢仕上げ・ヘアーライン仕上げ・梨地仕上げなど、仕上がりの視覚的効果が様々に異なってきます。金物では研磨などの前処理の出来・不出来やその方法の適切・不適切が外観上の製品の価値を左右します。また、研磨は相当な技術を必要としコストに関わってきますから、最終製品の仕上がり効果を考慮に入れた研磨方法を選定することが大切になってきます。 |
バフ研磨
バフ研磨は、何枚も重ねた布製の研磨車に研磨剤を付着させ、それを高速回転させ、製品の表面研磨を行います。メッキ前の下地処理やメッキ後の艶出しとして用いられます。(右図)
従来、荒研磨・中研磨・仕上げ研磨の三つの段階に分けられましたが、今日では優れた光沢メッキ薬品の発達により仕上げ研磨を省略することが多くなりました。このバフ研磨により鏡面仕上げ・光沢仕上げ・ヘアーライン仕上げ・サテーナ仕上げなどの仕上げ効果を得ることが出来ます。
科学梨地
液体ホーニング(科学梨地)は、腐食性の溶液と研磨剤とを混合したものを、圧縮空気でノズルから高速度で製品表面に吹き付け、仕上げ面を得る方法です。なめらかな梨地状の表面を得るとともに短時間で酸化皮膜を取り除くことができるので、メッキや塗装の下地処理に用いられます。
|
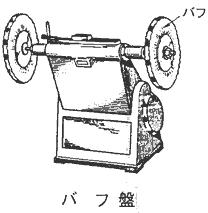 |
素地研磨の種類②
バレル研磨
バレル研磨は、回転バレルの中に研磨剤とともに製品を入れ、回転させながら研磨する方法です。
バリの除去・荒研磨・中研磨・艶出しなどの処理ができます。
光沢という点では、バレル研磨より劣りますが、大量の部品や小物を処理するのに適しており、非常に経済的です。
また、複雑な曲面を持った製品を変形させること無く容易に研磨できる点も特徴です。
電解研磨
電解研磨は、電気メッキとは逆の作用によって製品の表面の磨きを電気化学的に行う方法です。研磨しようとする製品を陽極として電解液中に吊るして電流を流すと、製品の表面は溶解し陰極に金属が析出して次第に表面が滑らかになり、最終的には鏡面光沢が得られます。
ステンレスや銀製品などではそのまま最終処理として使用され、アルミや鉄などの製品ではアルマイトやメッキの下地処理として用いられます。
欠点としては、素材の加工によって方向性が光沢面に出やすいこと、広い平面物はムラになり易いことなどが挙げられます。
![]()
メッキ
溶融メッキ
電気メッキ
無電解メッキ
塗装
手吹き。紛体塗装。静電塗装等
アルマイト
電解着色・有機着色
バフ研磨。バレル研磨。科学梨地。鏡面研磨。ショット等
熱処理(焼き入れ、焼きなまし)